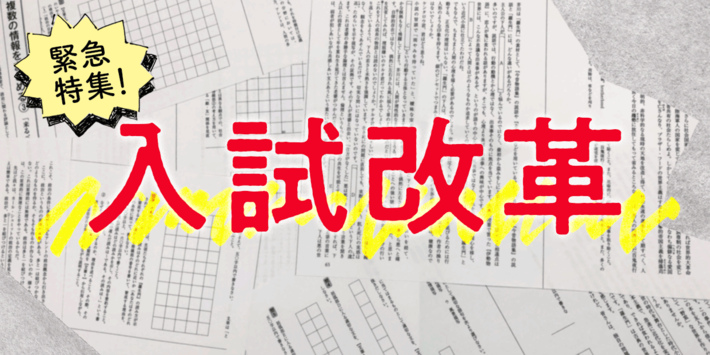†混乱する大学入学共通テスト
入学選抜制度の改革では、推薦入試やAO入試も名称や定義が改められることになりました。とはいえ、推薦入試やAO入試はやはり一部の人たちに限定されます。かろうじて具体案が見えるのは、一般入学試験です。なかでも最大の受験者数を誇り、入学試験のなかの入学試験とも言える「センター試験」を廃止して、「大学入学共通テスト」に改めるという。マイナーチェンジではなく、まさにメジャーな大改革だからこそ、名称まで変えてしまうというのです。
少し引いた視点で見てみると、逆にも見えます。最初の頃、教育再生実行会議や中央教育審議会、高大接続システム改革会議などの諸会議や議論では、生徒たちの能力をはかるには年に複数回の受験ができる方がいい、一回だけの試験では測りきれない能力があるはずだ、もっと多様で、実践的な能力を測る方法を探ろう、といったナイーブな意見が出ていました。ところが、アドバルーンはあがっても、実際に導入可能かというとうまくいかない。名称を変えるぐらいの大改革にしようという目論見であったのに、だんだん尻すぼまりになってきた。だからこそ、大きな改革に見えるポイントだけは残したいとでも言うかのような最終案になってきました。
その眼目は三つです。すなわち、
- 「英語」における民間試験の導入
- 「数学」における記述式試験の導入
- 「国語」における記述式試験の導入
の三種類です。「英語」では四技能を均等に評価することを目指し、なかでも試験形式にもっともなじみにくい「話すこと」(スピーキング)の能力を、民間業者による各種検定試験での結果で測るという。
「英語」の民間試験導入については、2019年11月1日、文科省より延期と見直しが発表されました。計画が公表された数年前から多くの疑問や批判が寄せられていた通りです。目的も質も異なる複数の検定試験をどうして一律の基準にあてはめることができるのか。検定試験の実施会場は当然、大都市圏に集中していますから、地域によって受検機会の偏りが生じます。検定料も別途、支払わなければなりません。抗議活動もさかんに行われました。
全国高等学校長協会は2019年7月に、文科大臣宛の「大学入試に活用する英語4枝能検定に対する高校側の不安解消に向けて」という要望書を提出し、「教職員をはじめ、生徒・保護者からの問い合わせにも、校長として責任ある回答ができず、説明に苦慮している」実情を訴えました。
折から、大学入試センターが認定していた試験実施団体のなかで、「TOEIC L&RおよびTOEIC S&W」という民間試験を実施する国際ビジネスコミュニケーション協会が、「大学入学共通テスト」の英語成績提供システムへの参加を取り下げることを発表しました。民間業者にしても、入試に用いる以上、公平性・正確性を期さなければならないことは百も承知しています。その分、リスクも高まります。ビジネス・チャンスとはいえ、突然の市場拡大ですから、受検者数も読めなくなりますし、全国津々浦々の会場確保もままならない。その上に大学入試センターと結ぶ契約内容に不安を抱えたからでしょう。結局、こうした不安や批判に加え、高校生まで声をあげ、文科相の失言によってついに進退きわまったのです。
「数学」や「国語」についてはどうでしょうか。記述式試験は、「センター試験」と同じマークシート式の試験問題の上に、新たに大きな問題一つを加えるかたちで導入されることになりました。これまでとまったく違う試験形式になるため、どのような試験になるか、サンプルの問題が公表され、さらに2017年と18年の二回、いずれも11月に一部の高校生を対象とした試行調査(プレテスト)が実施されました。そしてこれらの調査で用いられた試験問題が実施後に公表されたのです。実は、これが具体案の見えない教育改革で何が求められているかを探る唯一の手がかりなのです。
「大学入学者選抜が、高等学校や大学の教育に大きな影響を与えて」いるのだとすれば、それを一変させる試験問題が今後の高等学校や大学の教育の質や内容、方向性を示唆することになります。皮肉なことに入試問題が「国語教育」のこれからを示す指標となったのです。私が前著で2017年のプレテストやそれ以前に公表されていたサンプル問題を分析するという、赤本の解説者のようなことをしたのはこのためでした。
さて、それでどうだったか。つぶさにサンプル問題二つと一回目のプレテストの問題を分析し、検討した結果、いずれも入試問題として、これまでの「センター試験」の問題より劣ると結論せざるを得なかったのです。なかでも記述式試験の問題には内容、設問、解答、採点の四つともに大きな疑問符をつけざるを得ませんでした。さらにそれに加えて、旧来のマークシート式試験の問題においても、さまざまな「資料」を組み合わせて、「複数の情報を統合し、構造化する」能力を問うという厄介な課題がすべての問題にふりかかり、おそらくその強制力をはね返すことができなかったため、奇異な問題文や設問が並ぶという事態になりました。サンプルであり、モデルとなるべき、大学入試センターとしても相当に作成に力を注いだはずの試験問題で、このような結果になったのです。
†第二回プレテストの「国語」
2018年11月10日、土曜日の午後、「大学入学共通テストの導入に向けた試行調査(プレテスト)」が実施されました。前年の同時期に行ったプレテストの二回目にあたり、高校二年生と三年生を対象に、まず「国語」と「数学」(数学Ⅰ・数学A)の試験。ついで翌11日、今度は高校三年生のみを対象に、「数学」(数学Ⅱ・数学B)、「地理歴史、公民」、「外国語」(英語)、「理科」(物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から二科目)、「理科」(物理・化学・生物・地学から二科目)を組み合わせた試験が実施されました。1453校が協力し、約6万8000人が受験したのです。 では、「国語」はどのような問題が出題されたのでしょうか。 今回も第一回プレテストと同じく、第1問から第5問まで、大きな問題が五種類でした(試験時間はセンター試験よりも20分増えて100分となっています)。その試験問題となった材料の内訳は以下のようになっていました。
受験生は、こうして全部で13種類の「資料」や「文章」を読みました。ちなみに第一回のプレテストの「国語」では、全部で12種類、ただしそのなかには文章中に表や図、写真が入っているものもあり、種類でいけばもっと多くのものがありました。問題冊子のページ数としては、同じく52ページです。大差のない分量ですが、「センター試験」と比べると格段に増えています。
ここで取り上げるのは、第1問と第2問です。第1問は新たに導入される記述式試験の問題ですから、このプレテストにおいても目玉となるものです。そして第2問は、この間、強調されてきている「実用的」な文章を組み入れた問題文となっています。この二問に今回のプレテストの勝敗がかかっていると見るからです。
記述式試験にあたる第1問は、前回のプレテストやサンプル問題と傾向が大きく違いました。前回までの記述式問題で中心に置かれていたのは、次のような資料でした。
| サンプル問題の例 1 | 城見市「街並み保存地区」景観保護ガイドライン |
| サンプル問題の例 2 | 管理会社と交わした駐車場の契約書 |
| 第1回プレテスト | 青原高校の生徒会の部活動をめぐる規約 |
いずれも無署名の「実用的」な文章で、問題作成委員の人たちによって創作されたものでした。ところが、今回は実験心理学の鈴木光太郎さん、霊長類のコミュニケーション研究で知られる正高信男さん、言語学の川添愛さんというそれぞれ活躍中の学者による署名入りの文章が題材にされたのです。これは予想外のことでした。のちにまとめられた大学入試センターの「問題のねらい、主に問いたい資質・能力及び小問の概要等」によれば、「実用的」な文章は第2問の出題へと移り、記述式試験と「実用的」な文章とは必ずしもペアではないと説明がなされることになりました。
そうした変更はあったものの、大量の異なる種類のテクストを読むことには変わりありません。第4問や第5問にある「生徒と教師の会話」や「生徒ABCの会話」といったオリジナルの対話形式によるテクストは、やはりサンプル問題以降に見られる、一貫した共通要素です。古典を対象にした大問でもしばしば用いられていました。それぞれの大問で取り上げられた資料をめぐって生徒と教師が議論したり、A、B、Cといった三人の生徒が資料について対話したりしている場面が、問題文以外にべつの資料として配置され、それを読んで、また設問に答えるようになっていたのです。
これらは、どういうわけか「言語活動の場面」と呼ばれています。疑似対話を「言語活動」ということにしようというわけです。こうした対話文が果たして試験問題において意味があるかどうかはひとまず問わないことにしましょう。しかし、これほどさまざまな試験にくりかえすということは、対話を入れないではおられない問題作成委員のオブセッションがあるのだと理解しておきたいと思います。
†題材選択の本気度
では、第1問を見ていきましょう。この大問は「ヒトと言語」というテーマの話から始まります。問題文の前には、このような説明がついていました。
架空の人物である「まことさん」が登場し、二種類の文章を並べて読むという設定になっています。サンプル問題でも第一回プレテストでも、「かおるさん」や「サユリさん」、「森さん」という虚構の登場人物を媒介にして対話が展開するという奇妙な場面設定が共通要素としてくりかえされました。この奇妙なルールに拘っているのです。広い意味では「言語活動」重視の典型です。しかし、宙に浮いたような虚構の「言語活動」です。フィクションとしては、出来の悪い小説としか言いようがありません。総じて彼らが「国語」から追放しようとしている文学のなかで、もっとも低いレベルに該当しています。これが悪しき文学のサンプルなのだということを、大学入試センターも文科省も気づいていないところに大きな悲劇があります。
最初に引かれる資料は次の通りです。
ヒトは、ほかの人になにかを指し示すために指差し(ポインテイング)をする。驚く人もいるかもしれないが、これをするのはヒトだけである。
ほかの動物はこうした指差しをしないし、指差しの意味も理解しない。チンパンジーでさえ、野生では、指差しも手指しもすることはない。ただ、人間のもとで飼育されているチンパンジーの場合は、人間の指差しを教え込むと、その機能がわかるようにはなる。とはいえ、教え込んでも、欲しいものに手を伸ばすことはあっても、それ 以外でものを指し示すために指差しをすることはほとんどないようだ。
ヒトにとってはこれがあまりに簡単な行為なので、ふだんは考えてみることもないのだが、指差しで指示されている方向とは、指差した人間からの方向である。見ている側は、その指差した人間の位置に自分の身をおかないかぎり(あるいはそれを想像しないかぎり)、指されている方向やものは特定できない(これは「他者の視点に立つ」能力とも関係している)。私たちにはこれが簡単にできるが、ほかの動物ではそうではないのだ。
ここで、ことばを用いずに、指差しも用いないで、頭や目の向きも用いないで、相手になにかを指し示したり、相手の注意をなにかに向けさせたりする状況を考えてみよう。これはきわめて難しいことがわかる(ほとんど不可能かもしれない)。それとは逆の状況を考えてみよう。ことばのまったく通じない国に行って、相手になにかを頼んだり尋ねたりする状況を考えてみよう。この時には、A指差しが魔法のような力を発揮するはずだ。なんと言っても、指差しはコミュニケーションの基本なのだ。
指差しは、ヒトでは生後(11カ月頃から頻発するようになる。子どもは自分から指差しをし、またおとなが指差したものにも目を向けるようになる。指差しは、自分の関心のあるものに他者の注意を向けさせるための(「注意の共有」を喚起するための)強力な手段となる。これがいかに強力かつ自動的かは、「あっち向いてホイ」という遊びをしてみると、よくわかる。相手の指差した方向に目や顔を向けないようにすることは、頭ではわかっていても、きわめて厳しい。
最初の指差しの出現から1カ月かそれぐらいすると(1歳前後)、初語(注1)も出始め、この指差しの動作には単語がともなうことが多くなる。おそらく、こうしたB初期の指差しは、言語習得のひとつの重要な要素をなしている。
評論文としては内容においても文章においてもとても魅力的です。これまでの記述式試験の精彩を欠いた資料よりも、さすがに知的な刺戟に富んだ指摘が展開されています。
ほかの動物に見られないコミュニケーションの基本、それが「指差し」だと著者は言います。その「指差し」を通して、私たちは「他者の視点」を学び、強く身体反応を呼びさますようになる。コミュニケーションの基本とは単なる比喩ではなく、まさに身体にうめこまれたものを意味し、だから、無意識のうちに「指差し」の方向に目や顔を向けてしまうのだと言うのです。ここまで強い「指差し」を身につけたとほぼ同じ頃に、「言語習得」の始まりが起きる。「指差し」と「言語」の結びつきを説いたのが、最初の資料です。これを読んだとき、私は問題作成委員もようやく題材選択で本気を見せてきたなと思ったのでした。
†「指」が結ぶ三項関係
「指示」という言葉は「指」で「示」すと書く。何かを「指示」する、あるいは「指示」された対象というとき、私たちは「指差し」とともに起きる言語習得の過程を何気ない言い回しの奥に潜在的な記憶の痕跡として残しているのかもしれません。
もうひとつの資料は、やはり「指さし」に関連して、子どもと大人と指示対象という「三項関係」をめぐるものでした。
単語が意味を持つとは、指示対象が存在することを表している。名詞ならば、意味する事物が外界に存在する。子どもは「リ・ン・ゴ」と教わって、「リ・ン・ゴ」といえるようになっても、音の組み合わせが、くだんの赤い果物と対応していることがわからないと、「ことば」を話せることにはならないのである。
だから言語を習得するのに、大人と子どもが対面してコミュニケートするばかりでは、不十分となってくる。一つの語彙を伝えるには、当のことばの指示対象が眼前になくてはならない。つまり指し示すものを面前にして、かつ大人と子どもがともにそれに注意を向けつつ、指示する語を伝達して初めて、ことばの意味が伝わる素地がで き上がるのだ。こういうように、周囲の大人の指示行為に理解が及ぶようになったとき、子どもは一般に、「三項関係が形成されるようになった」と発達上、呼ばれることが多い。
ただ、モデルである単語とその指示対象との対応関係の把握は、容易そうでいて実はさほどやさしい作業ではない。子どもの生活世界は、ものにあふれている。ある単語を耳にしたとき、彼らは無数の潜在的な指示対象の候補のなかから、適切な一つを選択しなければならないのである。しかも大人は、英語の先生が生徒にしてみせるよ うに、本を手にとって‶This is a book." と教えてはくれない。
おのずと子どもの方から積極的に、「コレナニ」とたどたどしくとも答えを大人に求める必要に迫られることとなる。そこで、子どもが身体的動作による指示行動を行うようになるかどうか、ということが、言語習得の上でたいへん重要な意味を持つこととなる。だから「指さし」の形成が求められることとなる。
指さしとは、外界の対象物を定位しつつ腕を伸ばして「あれ」と指し示す行動のことである。地球上のおよそ八割以上の文化内で、人は人さし指を伸展させることで指示行動として用いているといわれている。この事実から、ヒトを他の生物から分かつ特徴の一つは、自分の身のまわりにある、さまざまな事物の存在を他者に伝達しうる点にあると、古くからいわれてきた。また、単に存在を伝えるばかりではない。対象を自己と他者がともに知覚し、対象がもたらす同一のイメージを持つ機会が提供される。結果として個々人の心のなかの認識世界に、何がしか互いに分かち合い、文化と呼べるような現象が芽ばえる素地が与えられる。特定の対象への関心が共有される素地をはぐくむ点で、指さし行動の出現は発達的にエポックメーキング(注1)な出来事と考えられるのである。
ここで著者は、「ヒトを他の生物から分かつ特徴の一つ」を「自分の身のまわりにある、さまざまな事物の存在を他者に伝達しうる点」にあると言います。そこで指示された「事物」に特定の「語彙」が貼り付けられるのです。これはなに? と問う子どもに、大人がこれは「リンゴだよ」と答えることで、リンゴという語彙と指示された対象の関係を飲み込むことになる。それを著者は「対象がもたらす同一のイメージを持つ機会」だと言い、双方がそのイメージを分かち合うことによって、コミュニケーションが成り立つというのです。
一方の鈴木さんは「指差し」という漢字二字を交えて記し、正高さんは「指さし」という漢字一字の表記を用いています。あえて同じに統一していないのですが、これはただ原文尊重という意図だけではないと思います。同一の表記ではない、しかし、この二つの言葉が指し示しているのは同じ行為、またそのイメージであることをさりげなく語っているのです。著者が違えば、おのずと表現も違ってきます。この二つの文章は、文体にも違いがあります。しかし、共通する主題が論じられています。これを結び合わせて考察をさせたい。少なくとも、問題文の選定において、当初、この第1問はなかなかやるじゃないかと思わせてくれました。
†記述式のリスク
さて、いかにも「国語」の試験問題らしく傍線が引かれていたのは【文章Ⅰ】だけでした。その【文章Ⅰ】から最初の設問が出ています。
【文章Ⅰ】を読んだとき、いいなと思いつつも、「指差しが魔法のような力を発揮する」という部分に傍線が引かれていたので、かすかな懸念を抱いたのでした。これは「魔法のような力」という比喩の中身を尋ねただけの質問です。センターは正答率70%を目指した設問だと、のちに自己解説をしていますが、それにしてもかなり平易な問いです。
すぐ直前の一文では、「ことばのまったく通じない国に行って、相手になにかを頼んだり尋ねたりする状況」を想像せよとありました。ここから要素をつまみ出して要約すればいいだけのことです。発表された正答の例は以下の通りでした。
今回、記述式試験においては、第一回以上に、正答の条件が明確化され、その組み合わせも細かくなっています。正答の条件として、まず次の三つの要素が用意されました。
この三つの条件に照らし合わせて採点がなされたのですが、その条件の組み合わせをめ ぐって、四つの段階によって採点する形式が取られました。すなわち、
条件③を満たしている解答(②は満たしていない)
ふーむ。しかし、これに当てはまらない解答もいろいろ想像することができます。たとえば、「指差しだけで言いたいことがすべて伝わってしまうこと」(25字)と書いてあったとします。これは条件①は満たしています。「指差し」に触れているのですから、条件②も満たしていると言っていいでしょう。しかし、「言いたいことがすべて伝わってしまう」ことと、「コミュニケーションがとれる、または、相手に注意を向けさせる」ことは同じではありません。「指差し」によって伝えられることは、コミュニケーションのなかでも内容的に限られています。ところが、この解答例では「すべて」としたので、どんなことも「指差し」で伝えられることになってしまいますから、正答にはなりません。そのときbではないが、cでもない解答に、どのような減点を行うか。判断の微妙に分かれるところです。
では、「ことばよりも指差しの方がコミュニケーションしやすいこと」(27字)だとどうでしょう。条件①、②、③のそれぞれと照合すると、条件を満たしてはいます。しかし、「ことば」と「指差し」の比較が論点ではありません。コミュニケーションしやすいかどうかも話題の中心ではないのです。つまらない、勝手な解答例をあげて困らせているだけでしょうか。実は記述式試験はこれだから厄介なのです。どのような解答が飛び出してくるか、予測がつかない。出て来たところで、検討し、その解答がどの段階の点数かを決めて採点します。手間もかかるし、不確定要素が出て来る。
このような平易な設問でも、そうしたリスクはつきまといます。正答率75.7%だから良かったとは言えません。残りの約24%のなかにどのような解答があったのか、75.7%のなかに右のような偏差がまぎれ込んでいなかったかどうか。検証できかねるのがこの試験の難点です。しかも、受験生は終了後の点検で、自分の解答が例の1~3のどれにも当てはまらず、条件①~③でどれに当たるか、判断がつかない危険性もあります。自己採点と誤差が生じてしまう。実際の入学試験となったとき、記述式はやはり大きな採点リスクを負っているのです。
†論点整理の矛盾
二番目の設問はこのような不思議な問いです。
「まことさん」のノートに整理したことを想像しながら考えよという設問です。【文章Ⅰ】の言葉を借りると、「まことさん」という「他者の視点」に立ってみて考えようというわけですが、何のためにそういう想像が必要なのか、まったくよく分かりません。そんなことをしなくても、「初期の指差しは、言語習得のひとつの重要な要素をなしている」という指摘について、【文章Ⅱ】の内容を基に、次のノートの空欄に言葉を入れて、「子どもが「初期の指差し」によって言語を習得しようとする一般的な過程」を「四十字以内」にまとめなさい、という質問でも十分なはずです。よくよく余計な迂回をへて、受験生をはぐらかすことが好きなんだとしか思えません。これも問題作成委員に課された命令のひとつと考えられます。
ある単語を耳にする。
↓
しかも
大人は
↓
だから子どもは積極的に指差しをする。
これが「まことさん」のノートです。基本は教師の板書と同じです。【資料Ⅱ】のなかで「大人」という言葉は四箇所出て来ます。その三つ目に、「大人は、英語の先生が生徒にしてみせるように、本を手にとって‶This is a book." と教えてはくれない」という一文があります。これを言い換えれば正答にたどりつく。一見するかぎり、これもたいへん平易な設問だと言えます。
発表された正答は以下のとおりです。
例1が抽象度が高いのに比べると、例3にいたっては、本文の‶This is a book." を日本語訳しただけです。あまりにも単純です。しかし、「これが本だ」ではなく、‶This is a book." とそのまま書き写していたらどのような点数にしましょうか。英語のアルファベットは文字数にカウントできないとしますか。しかし、内容的には例3とまったく違っていないのです。
正答の条件はやはり三つになっています。
②(大人は)教えてはくれないということが書かれていること。
③ 指示対象と単語との対応関係が書かれていること。
そしてこの条件三つをめぐって、先の問1と同じような、段階による採点を行ったとありました。少なくともこれなら、‶This is a book." であっても間違いにはできません。また、指示対象と単語との対応をそのような抽象的概念で記さず、すべて他の具体例で書いたらどうするのでしょう。「本を手にとって「これが本だ」と教えてはくれない」というのも正解だとしたら、リンゴを手に取ってこれがリンゴだと教えてくれない、という答えでも間違ってはいないことになります。
しかし、実際の採点結果は、正答率48.5%でした。条件②か③かだけだったものが40.9%、無解答かまったくの誤答が10.6%だったそうです。なぜ、こんなに低いのかは検証の必要があります。論理的な関係が読み取れていないのだと決めつけるのはまだ早すぎます。「まことさん」の視点を想像するという、あまり意味のない手続きや、ノートに書きつけた論旨の空欄をうめるという設定の理解に戸惑ったことも考えられます。
この設問は、「しかも」や「だから」といった接続詞を用いることで、前後の文の論理的な関係を捉えさせようとしたと推測されますが、実際には「大人は」という言葉の使用箇所を調べて、照応させれば簡単に正解に至ることができたのです。そこに論理的な思考は特段の必要がなかったことも押さえておかなければなりません。
†複雑な条件はなぜ必要か
いよいよ記述式試験の最後の設問です。前回もこの三問目はもっとも文字数が多く、ぶれの大きく出てしまう設問になっていました。
(注)1 指示詞──「指示語」のこと。
さて、どうでしょうか。突然、分かりにくくなりましたね。また、「まことさん」の視点に立つことが求められます。彼はこの
†記述式試験の長所が消えた
資料となった川添愛さんの『自動人形の城 人工知能の意図理解をめぐる物語』という本はたいへん面白い本で、AIと言語をめぐる問題を扱っているものですが、じつはメインは副題にあるとおり、架空の王国の王子さまが侍女や家来たちを魔法で自動人形にされてしまって起きるコミュニケーションのくいちがいをめぐる物語です。ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』を下敷きにしているような物語と考えて下さい。川添さんは自然言語処理を扱う言語学者ですが、その言語学の観点からAIと人間の差異と共通点について研究されている方だそうです。そういう言語学者の書いた完璧なフィクションが本書です。その巻末にこの物語をめぐる解説がついていて、出題されたのはこの解説の一部からでした。
ですから、この本の面白いところ、優れたところは全部すっ飛ばして、「指さし」に関するところだけを抽出した、とも言えます。そういう使い方がいいかどうかと言えば、あまり推奨する気持ちにはなれません。著者に対する、あるいはその著作に対する敬意が感じられないからです。しかし、それはひとまず措きましょう。設問が整っていれば目をつぶってもいい。
①から④にわたる解答の条件をご覧ください。①は文字数の条件。一転して、②はわかりにくい文章です。ひとつの文のなかにいろいろなことをギュッとつめこみすぎているからです。まず「話し手が地図上の地点を指さす」行為について、「指さされたもの」と「話し手が示したいもの」とが同じでないケースとして考えましょう。たとえば交番と交番の地図上のマークは同じではありません。にもかかわらず、話し手が地図上のマークを指差せば、ああ交番に行きたいんだなと聞き手には伝わります。どうしてそうなるのかが設問の核心です。しかし、「メニューの例に当てはめて」という言い回しは、何をどう当てはめるのか、分かりにくい。一瞬、メニューにたとえて解答するのかなと誤解したほどです。
③と④は二文目についての条件ですが、③の「ただし」以下のところで目が点になりました。たとえば、話し手が「地図上の地点」、交番を指したとします。そこにあるのはただの交番のマークになるはずですが、聞き手はそれを、「ああ、それは何丁目の角にある交番だな」と分かった。それには少なくとも最低、地図記号の種類やルールを知っていないといけない。「話し手と聞き手が地図の読み方について共通の理解をもっている」ことが、互いのコミュニケーションの大前提だからです。しかし、それは除くと条件づけています。
たぶん、それは【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】で論じられていることに近づけなければならないからでしょう。つまり、その設問を通して、問い自体に向き合って考えさせることよりも、複数の資料をまたいで答えを見つけさせることに目的があるのです。そのために複雑な条件が用意されている。条件を設けることで、いろいろな可能性を考えることをあらかじめふさいでしまう。これでは記述式試験のもつ長所がすっかり台なしになってしまいます。ねじれた設問と言わざるを得ません。
†正答の幅が狭すぎる
では、大学入試センターが発表した問3の正答は、どうなっていたでしょうか。やはり、 ここでも三つの例があがっていました。
さて、どうお思いでしょうか。例(では「他者の視点に立つ」ことができた、例2では「指さした人間の位置に身を置く」ことで「同一のイメージ」を抱くことができた、例3では「指さされた人間が指さした人間の視点に立つ」ことができたというのが答えのポイントです。みな、同じ要素を抱えた正答例です。
まず【文章Ⅰ】の鍵になる一文を抜き出すとすると、「指差しは、自分の関心のあるものに他者の注意を向けさせるための(「注意の共有」を喚起するための)強力な手段となる」というところになるでしょう。「注意の共有」という言葉にとりわけ注意を共有すべきです(ダジャレではありません)。【文章Ⅱ】の鍵となるのは、最後のところ、「対象を自己と他者がともに知覚し、対象がもたらす同一のイメージを持つ機会が提供される。結果として個々人の心のなかの認識世界に、何がしか互いに分かち合い、文化と呼べるような現象が芽ばえる素地が与えられる」という二文に注意を向けましょう。結びの一文には、「特定の対象」に向けた「関心」の「共有」という言葉もあり、「指差し」行為が言葉の獲得につながる過程があざやかに語られています。
しかし、ちょっと待ってください。それは「他者の視点」に立つことでしょうか。「ともに知覚」すること、「互いに分かち合い」という言葉はあります。「共有」もある。でも、それは「指さした人間の位置に身を置く」ことと同じでしょうか。視点に立つことよりも、まずは地図の記号という「言語」を獲得していたから共有できたのではないでしょうか。
この微妙な違いは気になるところです。記号であれ、イメージであれ、それがある対象を示すものとして設定される、そうした「言語」ないし「言語」に準じた手段を獲得できたから、話し手の「意図」を想像して理解することができた。そこまでは分かります。しかし、それは「他者の視点」に立ったからではありません。「他者の視点」はどうやっても分からない。何のために交番に行くのか、写真の料理をほんとうに食べたいのかどうかは分からない。たしかに鈴木さんの文章には「「他者の視点に立つ」能力」という言葉はありました。ただし、それは「言語」に当てはまるような関係のコードを身につけ、「指さし」のコミュニケーションの体験があったから、「「同一視できないケース」でも「話し手が示したいもの」を理解できる」ようになったのです。
川添さんの本をよく読むと、「他者の視点」に立つというようなことは一切、言っていません。いや、そもそもそのような観点を排することで考え抜こうとした本ですから、この問題作成委員は著作の「意図」をまったく理解できていないと言えます。川添さんは機械による言語処理と人間の自然言語処理の差をとりあげ、機械に同じことをさせようとするとどういう手続きが必要かを考えることで、人間の「言語」能力のしくみを見極めようとしています。
たとえば、川添さんは「よくできる人」の行動という面白い課題を設定し、その行動を決めているのは「指示者の言った内容を聞くのではなく、「指示者が何をもっとも重視しているのか」を推測し、その大原則が達成できるように行動を選択できる」ことをあげています。一見すると、「他者の視点」に立つと言っているように読めます。ところが、すぐあとでそのようなことは「もちろん、万人にできるようなことではありません」と言い切っています。「このような判断を可能にするには、指示者との間で価値観を共有する必要がありますが、そのようなものは目に見えないですから、結局は自分自身の価値観に照らして推測するしかありません」とも書いています。おやおや、ですよね。
「自分自身の価値観に照らして推測する」ことと、「他者の視点に立つ」ことのあいだは近いように見えますが、深い隔たりがあります。ここを読んでいたら、あの正答は作れない。1から3までの正答例は、いずれも「他者の視点」に立つことのむずかしさ、絶対的な壁を見ることなく、いかにも爽やかに、校長先生の訓示で「思いやりをもちなさい」と言っているかのような軽々しさをまとっています。完全に間違っていますとまでは言いませんが、いい設問ですねとは到底、言えない。少なくとも、私がこれまで関わってきた高校の「国語」は、こうした微細な言葉の差異のなかに、大きな真実が潜んでいることを示唆する教科でした。
とすれば、条件③の「ただし」以降は不要だったのです。そして、そこにこそ正答に近い要素が含まれていたのです。その要素を削ったのは、言うまでもなく、採点作業を単純化したかった、複数の資料をまたいで情報の統合や構造化らしく見える解答にしなければならなかったからに違いありません。まったく、この設問は本末転倒を起こしていたのです。
†テストは所詮テストである
「大学入学共通テスト」を推進している人たちは、記述式試験について、どうも過剰な思い入れがあるように思います。たしかに、マークシート式ならば、四つか五つの選択肢のなかから一つを選ぶだけです。鉛筆をころがしてマークするのだって、四分の一か五分の一の確率で正答にたどりつく可能性がある。それで人間の能力をはかることができるのか。
教育再生実行会議や中央教育審議会などの報告書を見ると、そのような意見が漏れ伝わってきます。しかし、それはテストというものを作ったことがない、採点をしたこともない人たちによる、素人の発言にすぎません。「国語」の記述式試験をこれまで作り、採点してきたものであれば、その短所も長所も分かります。同じようにマークシート式の試験にしても、その設問や選択肢においてどれだけ思索をめぐらし、どのような工夫を凝らしてきたか。経験者たちには分かっているはずです。とりわけ、素材となる文章を読み込み、どこに問いを設けるべきか、どのような設問の組み立てによって、どのようにこの文章が読めるようになるか、そうした精読者たる受験生を想像しながら、問題を作ってきたのです。
記述式試験にはたしかにマークシート式にはない長所があります。しかし、その場合、採点は限られた数の生徒と、限られた数の、信頼感ある採点者の集団であることが欠かせません。58万人を対象に1万人が採点することなど、あってはならない。それは記述式試験への冒瀆であり、その形式で可能なことをないがしろにすることだと思います。
テストは所詮テストです。テストはその生徒たちの能力のせいぜい一部しかはかることはできない。記述式試験ではかることのできる能力は、マークシート式と同じではないですが、それもやはり一部にすぎません。そしてテストは所詮テストにすぎないという、ある種の断念に立ち、同時にその範囲のなかで、徹底して正確さと公平性を期するのが、試験問題を作成するプロフェッショナルの矜持です。もちろん、出題のミスや過ちは簡単になくせません。人間が作ることであり、同時に季節労働のルーティンだからです。長くこうした業務に携わってきた人は、大小さまざまな限界を感じてきただろうと思います。そして、その限界を最小限にすることに最大のエネルギーを注いできたのです。
今回のプレテストを含む「大学入学共通テスト」のプランには、そうした大人の常識に欠けるところがあります。おそらく10人から20人くらいの集団がこの問題作成に関わっているはずです。そのベテランたちを迷わせているものがあるとしたら、それは「大学入学共通テスト」はこうでなければならないという絶対的な命令があるからです。テストは所詮テストである、だからこそという気概を、目に見えないベールの向こう側にいる作成委員の人たちにほんとうは期待したいと思います。