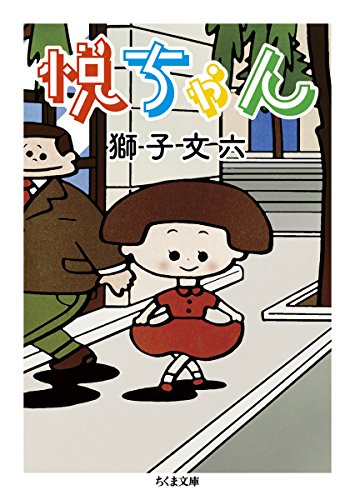そんなんでいいのか?
源氏鶏太の長篇小説『最高殊勲夫人』は一九五八年から翌年にかけて《週刊明星》に連載された。連載完結の年に講談社から刊行され、また映画にもなった。源氏鶏太原作・増村保造監督・若尾文子主演と、『青空娘』の三人が再結集した。
いま読むといかにも(内容に合わせて昭和な表現を選ぶならば)「C調」な物語だ。ストーリーのスタートのしかたも「そんなんでいいのか?」なら、ハイスピードなすったもんだの末の大団円も「そんなんでいいのか?」で、いちいち呆れてしまう。
なぜならこの小説は、小説として読むのではなく、一篇の「民話」として読むのが正しいからだ。
登場人物も多数、賑やかに進むラブコメの王道
大洋化学工業の経理課長・野々宮林太郎と妻・杉子の夫婦には、長女・桃子、次女・梨子、三女・杏子、そして高校生の長男・楢雄がいた。
三原商事の社長秘書だった桃子は、社長の長男で営業部長(のち社長)の三原一郎と結婚した。梨子も姉の後任として秘書室に勤務すると、一郎の弟で専務取締役の次郎と恋仲になり、結婚する運びになった。野々宮家三姉妹と三原家三兄弟のうち、それぞれ上のふたりどうしが結婚したところから、この「民話」がはじまる。
三原家の三男・三郎は、〈三原商事に入ると、一生、兄貴たちにこきつかわれるから嫌だといって、八重洲口にある大島商事に勤めていた〉。大島商事の社長は、梨子と次郎の結婚式の仲人だ。
三原商事社長夫人・桃子は、末の妹・杏子を三原三郎と結婚させたいという意志を明確に打ち出す。〈玉の輿の三重奏〉を狙っているのだ。そんなんでいいのか?
〈今日のあたしは、三原家の代表なんですよ。三原桃子です。そして、三原だって、この案には、大賛成なんですから。わたしの立場も考えて頂戴〉
三原商事の現社長の弟がふたりとも三原商事に揃えば、兄弟の結束によって、会社の将来のためにプラスになるだろうし、桃子の実家である野々宮家も、三原一族とのパイプが太くなるというメリットがあるだろう。って、そんなんでいいのか?
いっぽう、野々宮家三女・杏子も、三原家三男・三郎も、桃子をはじめとする周囲の人間の画策には乗りたくない。だからふたりとも相手に向かって、自分には恋人がいるのであなたとは結婚できない、と宣言してしまう。杏子と三郎は、そのように相手を欺きながら、しかし自分たちの結婚を阻止するために、いわば共闘することになる。そんなんでいいのか?
長女・桃子は妹・杏子の自由を阻む「敵」として暗躍する。そして杏子にも、三原商事秘書室勤務の話が降ってきた。
お似合いのふたりが意地を張って衝突ばかりしている。ラブコメの王道も王道なこの展開に、三郎の親友・風間圭吉、大島商事社長令嬢で三郎のガールフレンド・富士子とその兄・武久、三郎の行きつけのバーの女給・芳子、三原商事の前任秘書・宇野哲夫、営業課の野内稔、総務課の岩崎豊子、芸者・ぽん吉といった数多くの登場人物がからんできて、どんどん賑やかになる。
一九五〇年代日本の小説を読む楽しみのひとつは、そこに書きこまれた昭和の風情を読んでいくところにある。
一郎がよくないことをしに訪れる鬼怒川温泉の夜の風情。登場人物たちがありえない確率で「偶然の出会い」を重ねる銀座。「広い東京でそんな出会いがあるわけない」なんて言わないで、これらの場面は、どうか歌謡ショーでも見るような気持ちで読んでほしい。
また終盤の、野々宮家が銭湯を使っている場面を読むならば、現代の僕らは昭和感というか、懐かしい感じをいだいてしまう。その時代を生きていたわけでもないのに、なぜか懐かしい。そしてその感じを、もちろん当時の読者は感じなかったわけで(だってリアルタイムの風俗だから)、これは僕ら後世に生まれた者の得だ。
登場人物たちがやたらとんかつを食べるのも、これは宮藤官九郎ドラマのような畳み掛けと感じて、おもしろい。私見だけど、東京の人は関西の人に比べて豚肉が好きだし、豚肉のおいしい食べかたを知っている。
主人公たちの「民話」から「近代小説」への脱出
さて、桃子をはじめ周囲の、「杏子と三郎の結婚を望ましいと考える人たち」は、杏子と三郎の視点からは、「家と家との結びつきを個人の恋愛に優先させる旧弊な日本人」と意味づけられる。ふたりは第二次世界大戦後の新憲法が保障する両性の合意にもとづく結婚を重視したい。一九五八年に二一歳の杏子は、敗戦時に八歳くらい。
ふたりは家の一員としてではなく個人として行動しようとしている。民話の世界から、近代小説の世界へと、なんとか脱出しようとしている。
けれど杏子に味方する父・林太郎も〈これ以上、三原家の人に、娘を嫁がせたくありません〉(太字は引用者)と言うし、その杏子本人でさえ、姉たちが嫁いだ三原家の人と自分までも結婚したくない、と言う。三郎の行動の動機も、これ以上野々宮家との縁戚関係を重ねたくない、というものだ。
杏子と三郎は、相手が「すでに自分の姉・兄たちふたりと結婚している家の一員」だから結婚したくない、という意地の張りかたになってしまっている。皮肉な話だ。家の一員としてではなく個人で行動する近代人ならば、相手が好きなら恋に発展し、好きでないなら発展しない。相手の兄姉がすでに自分の家の縁戚になっているかどうかは、二の次であるはずだ。シンプルな話。
つまり杏子と三郎も「個人として行動する」ことができていない。「旧弊な日本人の《家》の命じることに反抗する」ことしかできていない。
そんなんでいいのか? これでは桃子同様に「家」に縛られてしまっているではないか。
いや、〈桃子も、梨子も、共に熱烈な恋愛結婚なのである〉と書いてある。お見合いでも政略結婚でもない。上の姉ふたりのほうが、よほど個人として恋愛および結婚を選択している。
これは、旧来の行動規範に反抗するばかりの「アプレ」の若者にたいする、連載開始時四六歳(敗戦時すでに三三歳)の作者のアイロニカルな構えなのか。
そう考えてしまうのは、小説の題の意味が最終段落で明かされるとき、「敵・味方」の構図が反転するのが、びっくりするほど鮮やかだからだ。
作者はのちに『源氏鶏太全集』第一五巻(講談社、一九六六)のあとがきで、つぎのように書いている。
〈はじめほんの数回の約束で書き出したのであったのに、いつのまにか二十四回になってしまった。「最高殊勲夫人」という題は、その頃、漫画家の西川辰美氏が何かの雑誌に「最高殊勲亭主」という漫画を連載していられたので、それにヒントを得、また、同氏の諒解を得てつけた題である。が、この小説の実際の主人公は、三人の娘のうちのいちばん下の杏子であり、〔…〕「最高殊勲夫人」という題は、必ずしも妥当でない。これも先に書いたように、数回のつもりが二十四回にもなってしまったせいである。ただし、私は、この小説の中に、夫婦のあり方とか、恋愛の手段方法ということも含めて書いたつもりである〉
『最高殊勲夫人』とは何者かを、作者は最初から決めていなかったのではないか。深く考えずに、つまりノリで、なんとなく威勢のいい語感に惹かれて連載の題を決めてしまって、最終回の最終段落で辻褄を合わせたのかもしれない。
この作品で作者が考える〈夫婦のあり方〉は、いかにも高度経済成長期らしい、核家族を単位とする性別役割分業だ。近年、なにかと悪口を言われているやつですね。小説は、書かれた当時の恋愛観・家庭観を反映することもある。
昭和と「家族的経営」の時代
この小説で、もうひとつ興味を惹く点について書こう。杏子と三郎を結婚させたい桃子は、つぎのように発言した。
〈ついでだから、三郎さんと杏子を、結婚させてしまいましょうよ。そうすれば、三郎さんだって、否応なしに、大島商事をやめて、三原商事に戻ってくることになるわ〉
〈戻ってくる〉? 論理上、三郎が三原商事に〈戻ってくる〉ことは不可能だ。だって三郎は三原商事に入社したことがない。三郎が三原商事に「移る」「転職する」ことはできるだろう。でも一度も在籍したことがない会社に〈戻ってくる〉ことはできない。
しかし桃子だけではなく、さまざまな登場人物が、三郎が〈三原商事に戻る〉とか戻らないとか、そういう言いかたをなんの疑問も持たずに使用している。企業と家との違いがきわめて曖昧なのだ。そんなんでいいのか?
この特徴はひょっとして、本書だけでなくて、他の源氏鶏太作品にも見られる可能性がある。けれど、源氏鶏太作品をそれほど多く読んでいないから確言はできません。
世界的に見て、近代初期の企業は、多く家族経営から出発した。また日本では江戸時代の、使用人も住みこみで同じ釜の飯を喰うスタイルが、明治以降の企業の自己像形成に影響してしまったようなところがある。企業の自己像がいわゆる「大店(おおだな)」だから、昭和は「家族的経営」の時代だった。
第二次世界大戦後の社会風俗を盛りこんだ娯楽小説でありながら、桃子たち周囲の人間の思考パターンは、時代劇の登場人物そのものだ。いや、思考だけでなく、じっさいに時代劇の世界だ。なにしろ小説の後半では、三原家との縁戚関係が娘たちの父・林太郎(善人だけど、男のプライドという邪魔なものに振り回される気の毒な人でもある)の去就に影響してしまうのだから。
現実世界でも、リアルな企業小説の世界でも、家族経営はなにかと確執を生む。ファミリー企業にお家騒動はつきものだし、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』(ビジネスではないが、三兄弟の世界観の相違の話だ)やコーエン兄弟のTVドラマ『ファーゴ』のセカンドシーズン(これこそ三兄弟のファミリービジネスの話だ)なんて、兄弟の思惑の違いが非常に厄介な問題を生み出していくさまを描いている。
だから現実世界だったら、桃子が思い描くような形での兄弟間の強まりが、三原商事にとっても三原家にとっても野々宮家にとっても、プラスになるという保証はない。
でもこの小説には、そんなリアルは必要ない。それはシンデレラや白雪姫の物語のあとに、結婚生活の危機というリアルが必要ないのと同じ。
そんなんでいいのか?
いいのだ。これは三原商事という小さな王国の王室と、心正しい平民・野々宮家にまつわる、素朴な民話なのだから。
(ちの・ぼうし 文筆家)